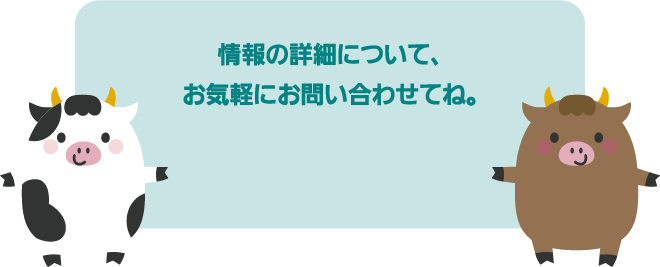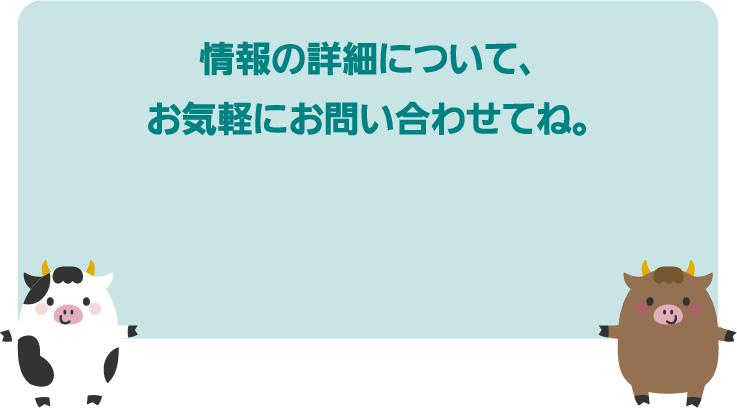牛は悪くない
北海道大学大学院農学研究院 小林泰男(動物機能栄養学・教授)
環境への取組
2021/12/1
2021年11月に英国で開催されたCOP26では温室効果ガス削減の標的としてとくにメタンガスに焦点があてられた。以前はCO2の23倍とされていたメタンガスの温室効果係数が、25倍に訂正され今に至るが、近年では28倍を使用する例が増えてきた。まさに今、世界中でメタンガス低減の取り組みにハイライトが当たっている。
世界のメタンガス排出の約31%が農業分野に由来し、さらにその約8割が消化管発酵からのものという統計がある(UNFCCC,2015)。消化管発酵由来のメタンのほとんどが反芻家畜の第一胃(ルーメン)由来であるため、牛のげっぷ経由で排出されるメタンガスの影響は小さくないということになる。CO2換算するとげっぷ由来のメタンガスは、地球上の全温室効果ガスの約4%に相当する(日本は牛の数が少ないため、この比率は0.5%以下と低いが、牛や羊の数が多いニュージーランドでは31%にもなる)。

《図1 世界のメタン発生源割合;UNFCCC2015データより作成》
こういった状況下で、昨今、牛の罪状が取りざたされ、「牛は気候犯罪者」なるレッテルまで張られる始末である。 「No Beef Monday(週1回は牛肉を食べない日をつくる)」「肉から代替肉や昆虫へ食の転換をはかる」といった運動が世界で展開中である。まさに過去1万年にわたる牛と人との共生関係を大きく揺るがせる事態となっている。先人は数多の野生動物の中から牛を選択し、手元に置き、選抜改良を重ね、彼らの生産物(主に乳肉)を巧みに利用(発酵・加工・成形なども含む)してきた。その過程で世界各地に独自の食文化が醸成され、今に至っている。少なくとも20世紀後半までは、牛を罪獣扱いすることは皆無であった。

現状に至った背景は単純である。著増する人口にともない畜産物の需要も増え、人は牛の頭数を増やしたが、温室効果ガス(メタン)の影響に気づくのが遅れたこと、に集約される。根本の原因である人口増加は止まらず、2050年には食タンパク質の需要が1.8倍(2010年比)に上昇する。悪いのは牛ではなく、情勢を見誤った人類のほうなのである。状況打破には、なるほど「牛を減らす」という発想は最もシンプルな策だが、これは「畜産業を縮小する」「食文化を滅ぼす」ことに外ならない。一方で、乳肉の代わりのタンパク源と期待される大豆や昆虫は、アミノ酸バランス、とくに必須アミノ酸のリジンやメチオニン含量で乳肉に劣ることから、乳肉の出る幕はまだまだ閉じてはならない。共役リノール酸やラクトフェリンといった健康に関わる機能性栄養素の存在も見過ごせない。乳肉の加工や調理の多様性には目を見張るものがあり、それらの歴史は世界の種々の民族の歴史と言っても過言ではない。
加えて(言うまでもなく)牛は草食家畜である。草の主成分セルロースは地球上で最大のバイオマス(千億トン/年)であり、かつ太陽光と水で再生産可能である。現状は穀物を併給する体系下で牛が飼われてはいるものの、将来は100%植物質飼料で生産を落とすことなく飼われる時代が来るはずである。少なくとも下記プロジェクト研究では(メタン低減とともに)草主体での飼養を目指している。つまり、近い将来、メタン排出最小化をうたう体系下で本来の草主体の飼い方に戻される日が、すなわち牛の主権回復の日が、来ることが期待される。

私たちは科学の側面からこのような状況打破を狙い、21世紀初頭からげっぷメタン低減に取り組んできたので、最近の極めて高い注目ぶりにはやや戸惑いすら感じる。しかし、ようやく認知が進み研究に拍車をかける予算支援体制が国内に整ってきたことには感謝したい。そのひとつがムーンショットプログラムへの採択である。ムーンショットは「従来の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発」を標榜しており、食供給と環境保全を両立するための課題(図2,3参照)として、私たちの「牛ルーメンマイクロバイオーム完全制御によるメタン80 %削減に向けた新たな家畜生産システムの実現」が選ばれた。そこでは、ルーメン微生物学に立脚した発酵の制御を機能性飼料などで実施するとともに、ルーメン内に留置する小型電子機器(スマートピル)による発酵様式の連続モニタリングを通して、牛個体ごとの精緻型給餌法をAIが提案するシステム開発を目指している。

《図2 プロジェクト研究の概念図》
牛ルーメンに留置したスマートピルが発酵を連続的にモニタリング、外部で受信、AIが個体別の最適給餌法(メタン低減飼料も含め、給与量と給与タイミングなどを自動給餌機に伝え、メタン最小化をもたらす)を提案する

《図3 食供給と環境保全を両立するための課題;牛は悪くない!》
メタン低減を導く機能性飼料素材としては、北海道大学と出光興産の共同研究で見出だされた「カシューナッツ殻液」を含有する製剤がすでに商品化されている(図4)。今後、現場でのバックデータを蓄積し、より説得力のある普及拡大に努めていく必要があるものの、日本発のメタン低減飼料第1号として、探索・評価→開発・普及のよいモデルとなるであろう。ただし、安全保障の意味合いから、メタン低減飼料は複数もっておくことも重要である。なぜなら、素材の量的確保に加え、機能の持続性などが重要だからである。すなわち、天然素材は気象条件によっては量的確保が困難な時もある一方、素材の効果減退がみられる場合は別のメタン低減素材とローテーションで使用するなどの工夫も必要になるかもしれない。

《図4 カシューナッツ殻液を含有する製剤》
私たちの食、とくにタンパク質源の安全保障の意味合いでも同じことが言えるだろう。大豆や昆虫だけでは心もとなく、乳肉を含めた複数のタンパク質供給源を確保しておくことが、将来より安心と考えられる。食文化的にも、栄養学的にも、また食の安全保障上も、「牛は悪くない」どころか、「牛の存続は必須」なのである。

【プロフィール】
小林泰男(こばやしやすお)
1956年5月28日生
出身学校:北海道大学農学部卒
現所属:北海道大学大学院農学研究院動物機能栄養学(教授)
研究内容:動物の栄養生理と環境負荷低減に関する研究
趣味:ランニング、スノーシューイング